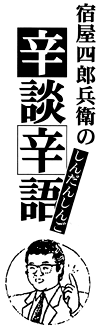 「売れた商品」の品質
「売れた商品」の品質
長い間「売る」ということに商売人は全精力を傾注してきた。もちろん、今もそうだろう。基本的に何かが「売れない限り」事業は成り立たないからだ。「小売は科学そのものだ」とは、しまむらの藤原秀次郎氏の言葉だと聞く。セブンイレブンの鈴木敏文氏も「売る」ための仕組み作りに卓越した手腕を発揮された。
商品が少なかった時代、商品が手に入り難かった時代、当然「商品を握っている商人」が主導権を取ってきた。誰もが欲しがる商品のルート(流れ)は、一部の人間にしか分からなかったからだし、そのルートは秘密性を帯びたものであった。問屋街の存在が、一般消費者には知られなくてもいいという論理だ。
誰でもが商品を取り扱うことができなかったし、その商品が欲しいと思っても「特別なルート」(縁故など)を持たない人の手には渡らないのが普通だった。
商品を持ってさえいれば(仕入れることができれば)、それだけでもビジネスは成功したのだ。
商品を店頭に置くだけで「飛ぶように売れた」時代が随分長く続いてきたように思う。まだまだ新道通りに溢れかえる人の流れを目の当たりにした記憶を持つ人は多いことだろう。
それでも「売る」ことについて「かなり厳しかったし、大変だったよ」との苦労談が付いている。内実は、「売る」ことより、「仕入れること」「モノを確保すること」が大変だった。売れた時代の「販売品質」だ。
「売れない時代」到来
「モノありき」の時代が長く続き、いつの間にか売れる商品の「販売品質」が変化した。このことは、誰もが頭では理解できても体が付いていかない、「まだまだ売れるはずだ」と自分に鞭を打ってしまう。
「こんなはずではない」「売れないのは、社員のやり方が悪い」「言った通りやらないからこんなことになる」、「一人一人が、あと1000円、あと5000円売ってくれれば前年オーバーするのに」「最低の予算も達成できたのに、今の社員は粘りがない」と、焦れば焦るほど数字は付いて来ない。従来の型の「成長戦略」「競争戦略」が通じない時代になった。
トップの言うことが社員には理解できない、「そんなことは百も承知のこと、叱るだけでなく現場をよく見てくれ」、言われなくても、トップも心配で次々と店舗を巡回する。しかし、やることは店舗スタッフのあらさがし?に終始してしまう。
「なぜこんなところに商品が置いてあるのだ」「在庫が多すぎる」「ショウイングが悪い」「一体売る気があるのか」等々、結局、個人批判に終始してしまう。まだ、努力すれば、工夫すれば売れるはずだ。誰もがこの“神話“を信じようと必死になってしまう。
現に「売れている商品」も「売れている店」も多くの新聞や雑誌が、これでもかと紹介しているではないか。
論理としてのモノ作り
ここまで、なぜ分かり切ったことを書いてきたのか、「そんなこと百も承知よ」との声が聞こえそうだ。
だが、ここで皆さんに考えてほしい。どんな企業も「販売=売上高」無くして企業は成り立たないのが資本主義の原則だ。そのため、企業から商品を見る目は、常に「提供する側=作り手」の目線なのだ。「売れるモノを作る」が至上命題となる。
企業組織そのものが、商品を作り、それを販売して利益を上げていくようにできている。どうしても「売れる商品を作り出す」宿命を背負っていると言わざるを得ない。
社員もそのために採用し、給料を払っているのだ。社員も与えられた使命を完遂すべくシャカリキになって、只管に売れるかどうか分からない商品を、とにかく予算に合わせて企画・生産する、仕入れる、そして在庫として残す。
これらの商品が今の時代、売れる確率が極めて低いことも承知の上ながら「万一」当たることもあるかも知れない。作らない限り売れることはない。
企業の論理は、つねに「攻め」であることが問われる。大手アパレルなど年間に考えきれない数のブランドを発売し、その多くを翌年にはスクラップにしている。ブランドを出すことが、株価を維持し、株主の利益を守ることに繋がるからだ。
「売れるための発想法」
昔から、「販売の達人」と言われた経営者には、意外なことに「守り」を得意とするタイプの人が多い。
「守り」とは、徹底してお客様の声を聞き、それに合わせてモノを作ってきた人だ。販売感覚が徹底していて「お客様をよく知ること」で磨かれている。自分のカンやセンスなどを「販売品質」にしない人達だ。
もっともカンは馬鹿にはできない。天才的にカンを働かせてビジネスを成功に導く人も皆無ではない。問題は、そのカンがどこで磨かれたのかということではないか。
通常、何が売れるかのカンは消費者が何を好むかのカンであって、天才的、芸術者的カンというのは、あまりにも自己中心的であり、売れるものが生まれる可能性は少ない。いわゆる「販売におけるカン」とは別の世界のものだ。
「販売におけるカン」は、普段から消費者の苦情に耳を傾け、そこから何を消費者が欲しているのかを「着眼」するという習性ができていると言えるのかも知れない。天才と言われる存在とは程遠い気がする。商売上手と言われる人は、概して街を歩き回り、評判の商品には必ず手にとって、触ってみる。
この体験が多ければ多いほど「売れる商品」を「販売品質」にする確率が高まるのだ。
人間は“不満”に敏感
消費者が“満足”には鈍感だが、“不満”には極めて敏感であることは、自分自身のことを振り返ってみれば納得できる。
今をときめくユニクロであろうと、海外ファストファッションの代表H&Mやフォーエバー21であろうと「販売品質」向上への一瞬の油断が、これらの店頭から消費者を去らせてしまうことになる。
海外トップレベルの展開する「販売品質」レベルは、そのファッション性において、そのショップ店員の販売レベルにおいて、現在の日本の消費者が求めるレベルをはるかに超えている。その証明が、オープンに際しての長蛇の列となる。
消費者は多くの日本の従来型ショップ、百貨店やGMS、また専門店の多くに共通する「販売品質」のレベルの低さ、欲しい商品を作り出せない体質に多大の不満を堆積させていたに違いない。
日本を、いや世界を覆う不景気の嵐にもかかわらず、ファッションに対する消費者の意欲は決して衰えてはいないのだ。むしろ、さらなるファッション・レベルの進化を求めていたに違いないことが、別表に掲げたファストファッションにおける「販売品質」によく表れていると見るべきだ。
ファストファッションの「販売品質」こそ、現下の消費者が求めて止まない「売れる商品」そのものだ。

